事業運営において大きなコストとなる高圧電力の電気料金。昨今の燃料費高騰や社会情勢もあり、その負担は多くの企業にとって深刻な経営課題となっています。しかし、高圧電力の料金体系を正しく理解し、適切な対策を講じることで、電気料金は大幅に削減することが可能です。
この記事では、企業の経営者様や総務・設備担当者様に向けて、高圧電力の料金の仕組みといった基本から、今すぐ着手できる契約の見直し、効果的な設備投資まで、電気代を削減するための具体的な9つの手法を専門家の視点から徹底解説します。
まずは基本を理解する|高圧電力の料金体系の仕組み
効果的な節約術を実践する前に、まずは自社が支払っている電気料金の内訳を正確に理解することが不可欠です。高圧電力の料金は、主に「基本料金」と「電力量料金」という2つの要素で構成されています。
電気料金を構成する2つの要素:基本料金と電力量料金
- 基本料金:
毎月の電気使用量に関わらず発生する固定費です。後述する「契約電力」の大きさに基づいて算出されます。つまり、電気を全く使わなくても支払わなければならない料金です。 - 電力量料金:
実際に使用した電気の量(kWh)に応じて変動する変動費です。この料金には、発電に必要な燃料の価格変動を反映する「燃料費調整額」や、再生可能エネルギーの普及のために国民全体で負担する「再生可能エネルギー発電促進賦課金」も含まれます。
基本料金の鍵を握る「デマンド値(最大需要電力)」とは?
基本料金を決定づけるのが「契約電力」であり、この契約電力は「デマンド値」によって決まります。
デマンド値とは、30分間の平均使用電力(kW)のことです。電力会社は、24時間常にこの30分デマンドを計測しており、その月における最大のデマンド値と、その前の11ヶ月間の各月の最大デマンド値を比較し、その中で最も大きい数値が、向こう1年間の契約電力として採用されます。
重要なのは、一度でも大きなデマンド値を記録してしまうと、その後1年間、たとえ使用電力が少なくても、その高い基本料金を払い続けなければならないという点です。つまり、基本料金を削減するには、このデマンド値をいかにコントロールするかが最大の鍵となります。
契約見直し編:固定費である「基本料金」を削減する方法
まずは、比較的短期間で効果が見えやすく、設備投資も不要な契約内容の見直しから着手しましょう。
1. 新電力(PPS)への切り替えを検討する
2016年の電力小売全面自由化により、多くの「新電力(PPS:Power Producer and Supplier)」が市場に参入しました。これらの事業者は、地域の大手電力会社よりも割安な基本料金単価や電力量料金単価を提示している場合が多く、電力会社を切り替えるだけで大幅なコスト削減が期待できます。
複数の新電力から見積もりを取り、自社の電力使用パターンに最も合ったプランを比較検討することが重要です。インターネット上の一括見積もりサービスなどを活用すると、効率的に比較ができます。
2. 契約プランの最適化
現在契約している電力会社内でも、より有利な料金プランが存在する可能性があります。例えば、休日や夜間に電力使用量が多い工場であれば、その時間帯の料金単価が安いプランに変更することで、全体の電気料金を抑えられるかもしれません。現在の電力使用状況のデータ(電力会社のWebサービスなどで確認可能)を持参の上、契約中の電力会社に相談してみるのも有効な手段です。
運用改善編:変動費である「電力量料金」を削減する方法
日々の運用を見直すことで、デマンド値を抑制し、使用電力量そのものを削減します。
3. デマンド値を抑える(ピークカット・ピークシフト)
- ピークカット:
電力使用量が最も多くなる時間帯(ピーク時)に、意図的に電力使用を抑えることです。例えば、複数の大型機械を同時に稼働させない、昼休みの時間帯は空調を一斉に弱める、などの工夫で電力需要の山を平らにし、デマンド値の上昇を防ぎます。 - ピークシフト:
電力需要のピークを、電力料金単価が安い時間帯や他の設備が稼働していない時間帯にずらすことです。例えば、生産計画を調整し、一部の稼働を夜間に移すなどの方法が考えられます。
4. 省エネ活動の徹底
全社的な取り組みとして、地道な省エネ活動を徹底することも重要です。
- 照明の間引き、こまめな消灯
- 空調の温度設定の最適化(環境省推奨:夏28℃、冬20℃)
- クールビズ、ウォームビズの推進
- 使用していないPCやOA機器の電源オフ、省エネモードの設定
- 業務用冷蔵庫の扉の開閉時間の短縮
5. デマンド監視装置(デマンドコントローラー)の導入
デマンド値を人の手だけで管理するのは困難です。そこで有効なのが「デマンド監視装置」です。この装置は、現在のデマンド値をリアルタイムで監視し、設定した目標値を超えそうになると警報(アラート)で知らせてくれます。さらに高機能な「デマンドコントローラー」であれば、警報だけでなく、あらかじめ設定した優先順位に従って空調などの設備を自動制御し、デマンド値の上昇を強制的に防ぎます。導入には数十万円からのコストがかかりますが、確実なデマンド管理が可能になります。
設備投資編:長期的な視点で大幅なコスト削減を目指す
初期投資は必要ですが、長期的に見て大きなリターンが期待できる方法です。
6. 省エネ性能の高い設備への更新
古い空調設備(エアコン)、コンプレッサー、ポンプ、モーターなどは、最新の高効率なモデルに更新することで、消費電力を大幅に削減できます。消費電力が下がれば、電力量料金が削減されるだけでなく、デマンド値そのものを引き下げる効果も期待できます。
7. LED照明への切り替え
工場や倉庫、オフィスの照明を従来の蛍光灯からLED照明に切り替えることは、非常に効果の高い節電策です。LEDは蛍光灯に比べて消費電力が約50%以下と少なく、寿命も数倍長いため、交換の手間やコストも削減できます。
8. 太陽光発電設備(自家消費型)の導入
工場の屋根や敷地内に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を自社で使用する「自家消費型太陽光発電」も有力な選択肢です。電力会社から購入する電力量を直接的に削減できるため、電気料金を大幅に引き下げられます。また、災害時の非常用電源としての活用(BCP対策)や、環境貢献企業としてのアピール(ESG経営)にも繋がります。
9. 蓄電池の導入
太陽光発電設備と蓄電池を組み合わせることで、さらに節電効果が高まります。日中に太陽光で発電した電気のうち、使い切れなかった余剰電力を蓄電池に貯めておき、夜間や天候の悪い日に使用できます。また、電力料金単価が安い夜間電力を蓄電し、料金単価の高い昼間のピーク時間帯に使用する(ピークシフト)といった活用も可能です。
節電施策で活用できる補助金・助成金制度
省エネ設備の導入には多額の初期投資が必要となりますが、国や自治体は企業の省エネ活動を支援するための様々な補助金・助成金制度を用意しています。
例えば、経済産業省が管轄する「先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金」など、大規模な設備投資を支援する制度があります。設備導入を検討する際は、必ず専門の業者や地域の商工会議所などに相談し、活用できる公的支援制度がないかを確認しましょう。
まとめ:自社の状況に合った最適な節約術で、経営体質を強化しよう
高圧電力の電気料金削減は、一朝一夕に実現するものではありません。「契約」「運用」「設備」という3つの側面から、自社の状況を正しく分析し、総合的に取り組むことが成功のカギです。
まずは、電力使用状況の「見える化」から始め、新電力への切り替えやデマンド管理といった比較的着手しやすい施策から検討してみてはいかがでしょうか。電気料金というコストを戦略的にコントロールすることは、不安定な経済状況を乗り越え、企業の経営体質を強化するための重要な一手となるはずです。

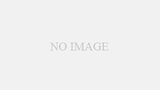
コメント